2020年01月29日
バニスター代表の細谷正人が新たな視点でブランディングデザインに斬り込み、先進企業に取材する連載「C2C時代のブランディングデザイン」。番外編として、連載に大幅に加筆して発刊した書籍『ブランドストーリーは原風景からつくる』の刊行記念イベントから、「Ginza Sony Park」を手掛けたソニー企業社長兼チーフブランディングオフィサーの永野大輔氏と細谷の対談を掲載。今回はソニーが考えるブランドづくりについて聞いた前編。

左からバニスターの細谷正人とソニー企業社長の永野大輔氏。対談は「Ginza Sony Park」で行った(写真/丸毛 透)
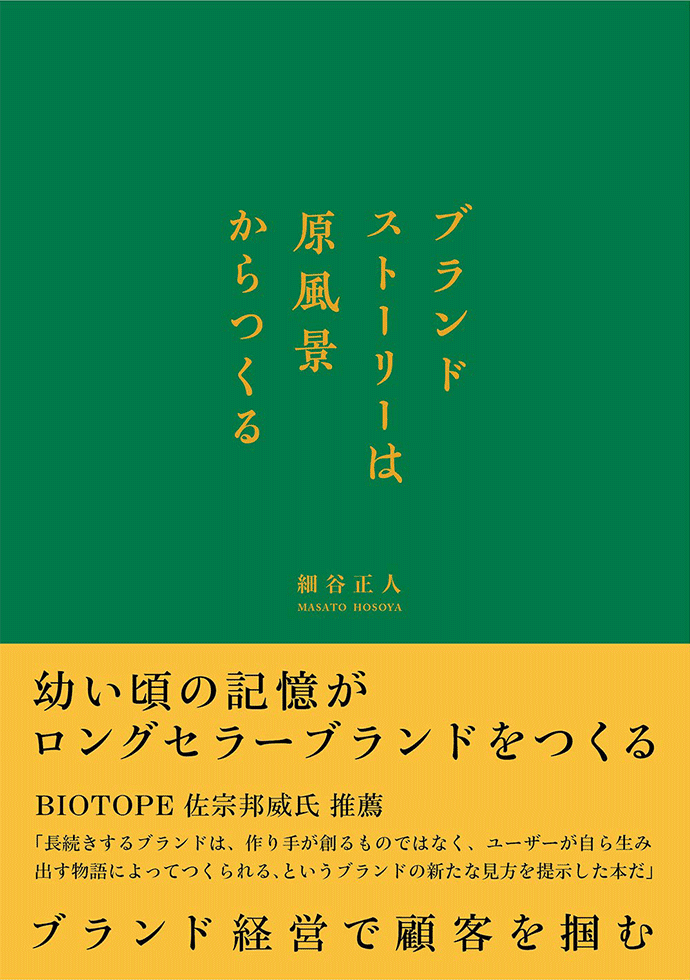
『ブランドストーリーは原風景からつくる』(日経BP)
細谷 書籍『ブランドストーリーは原風景からつくる』刊行を記念し、トークセッションを始めます。ソニー企業(東京・中央)社長の永野大輔さんには、書籍に掲載した「Ginza Sony Park」の事例として取材をさせていただきました。今回は改めて、書籍内で言及している「原風景」「自伝的記憶」という点について深めていきたいと思います。そのうえで、良いブランド、良いブランディングとは何かについてお聞きします。
まずは、私が言う原風景という言葉を説明します。これは文芸評論家でもある奥野健男さんが1972年に書かれた『文学における原風景』からきています。日本文学の中には、著者が描くさまざまな風景の描写が出てきますが、その風景の意味を読み取らないと文学の本質が見えないと奥野さんは書いています。例えば太宰治の小説『津軽』には、太宰自身が思い描いている津軽があり、それが文体に表れているそうです。同様に考えたとき、ブランドづくりにもユーザーそれぞれの体験、つまり原風景を意識する必要があるのではないかと思いました。
私は大塚製薬工場の「オロナインH軟膏」など多くの商品のブランディングを手掛けてきました。このときユーザー調査をすると、それぞれのユーザーにいろいろな原体験があることが分かりました。オロナインH軟膏でいえば、実家にある薬箱のシーンとか、親から「オロナインを塗っておきなさい」と言われたとか、そういったユーザーの原体験があるからオロナインH軟膏に対するブランド愛着が非常に高いのではないかと感じたのです。オロナインH軟膏だけではなく、他のロングセラーブランドにもユーザーの強い原風景があるのではないか。そんな疑問から、書籍『ブランドストーリーは原風景からつくる』が生まれました。
原風景を言い換えると、「自伝的記憶」という言葉になるのではないかと思います。これは私が定義し、記憶研究の中に出てくる言葉です。事実として記憶を捉えるのではなく、そこに主観的な心理性、つまり自分の思い込みを加えるというイメージです。自分で脚色し、いい思い出に変える行為も、自伝的記憶と言えるでしょう。実家のキッチンの風景、子供のときの運動会、親が作ったお弁当の思い出、旅行時の家族の顔など、いろいろな記憶が自伝的記憶となり、個人の原風景になる。さらに原風景に情緒的な記憶が存在すると、ほぼ無条件で生活者はその商品を購入してしまう傾向があるのです。
そういうふうに考えると、私にとってのソニーの自伝的記憶は、小学校3、4年生ぐらいにもらった「ウォークマン」になるんです。ピンクのウォークマンでしたが、今でも強烈な印象があります。
永野 私の価値観をつくっているような記憶、体験について考えると、小学生の頃に父親から教わったことかもしれません。それを一言で言うと、業界トップではなく2番手とか3番手であることの面白さや反骨心でしょうか。
例えば、テレビはソニーでしたが、車はホンダでした。父親が持っていた腕時計はカシオで、購読していた新聞は毎日新聞。当時は全く意識していませんが、父親はトップブランドではなく、2番目や3番目を選んでいたようです。松下電器(現パナソニック)ではなくソニー、トヨタではなくホンダ、セイコーではなくカシオ、読売ではなく毎日というわけです。1番はみんなが持っている。だからみんなとは違う2番とか3番の会社のほうがいいとか、2番や3番はチャレンジャーだから、応援したくなると言っていました。まぁ、ちょっとひねくれていただけなのかもしれませんが(笑)。
私がソニーに入社を希望したのも、常にチャレンジしている会社の姿勢に共感していたという潜在的な意識があったのだと思います。細谷さんの書籍を読んで、自分の原風景や自伝的記憶を考えると、そんな感じがしました。アンチテーゼというか反骨心みたいなものがあるのは今も変わらないですね。
細谷 ソニーの社員の方々は、永野さんのような原風景があるのでしょうか。

(写真/丸毛 透)
ソニー企業社長兼チーフブランディングオフィサー
1992年にソニー入社。営業、マーケティング、経営戦略、CEO(最高経営責任者)室などを経て2017年から現職。「Ginza Sony Park Project」のリーダーとして、13年からプロジェクトを推進し、18年8月9日に「Ginza Sony Park」をオープンさせた
永野 それぞれの社員が持っている原風景は異なると思いますが、ソニーらしさというのはあるかもしれません。1946年にソニーの前身の東京通信工業ができましたが、創業者の一人である井深大さんが書かれた設立趣意書の最初の文章の中に「自由闊達ニシテ愉快ナル理想工場ノ建設」という文言があります。「自由闊達」「愉快なる理想工場」というキーワードはソニーらしさの原風景になっていると思いますね。今でこそソニーは大きな会社ですが、もともとは戦後の焼け野原の中から出現したベンチャー企業です。だから、すごく夢を持った理想工場を目指していたんです。
設立趣意書以外に、創業者の一人である盛田昭夫さんが言っていたことでは、ソニーらしさとは商品ではなく、社員一人ひとりの中にあるプライドだと言っていたのですよね。社員はソニーがユニークな会社であることにプライドがあり、それがなくなった瞬間にソニーらしさはなくなるというわけです。だから、ユニークなことをしよう、チャレンジしたいという意識が自分の中にあります。
Ginza Sony Parkも同じです。東京・銀座にある「ソニービル」を壊して新しい建物を普通に造ったら、ソニーじゃない。すごく単純ではありますが、分かりやすい話ですよね。Ginza Sony Parkは2021年9月末をもっていったん終了し、25年に新しい建物にする予定ですが、その建物もコンセプトは公園です。今までの公園を「縦」に伸ばすことを考えています。
Ginza Sony Parkは18年8月にオープンし、1年間で400万人の方にご来園いただきました。400万人ということは1日1万人強です。目的を持った方と、目的を持たずに通り抜けただけの人、たまたま休憩場所を見つけて来た方もいたでしょう。成果を見ると本当に造ってよかった、成功したと実感しています。ソニービルの来訪者は年間で約350万人でしたから、公園にした価値はありました。

東京・銀座の真ん中にある「Ginza Sony Park」には、平日でも多くの人が集まっていた(写真は開園した当時)(C)Ginza Sony Park
永野 私はチーフブランディングオフィサーでもあるため、ブランド戦略のお話もしたいのですが、その原点はソニーとユーザーの関係性を考えることにあります。では、ユーザーに何を提供するのか。つまり「What」ですね。そして、それをどう提供するか。「How」が重要になってくる。しかしブランドで一番大事な点は、WhatやHowに加えて、「Why」ではないでしょうか。ソニーの存在意義、つまり社会やユーザーへの約束事が重要になるわけです。ソニーはこういう会社です、こういう会社になります、なりたいですといった、いわば「プロミス」です。これがブランドづくりの根幹だと思っています。
ではソニーのWhyは何か、プロミスは何かを端的に言えば、「ユニークネス」。つまり「人がやらないことをやる」ことです。そのためのWhatとは、商品やサービス、コンテンツによる感動体験を提供することにあります。だからHowは、洗練されたユーザーエクスペリエンス、楽しいエクスペリエンスになる。
ただし、ユニークネスを掲げていながら、商品やサービス、コンテンツがユニークじゃなく、感動体験にもつながらなければブランドには育ちません。同様に、感動体験につながる商品やサービス、コンテンツをつくっても、提供の仕方がまずかったらブランドとして認知されない。だからWhy、What、Howの3つを連係させることがブランドづくりで一番大事です。
(日経クロストレンド2021年06月4日掲載の内容を転載しています。)