2020年01月28日
バニスター代表の細谷正人が新たな視点でブランディングデザインに斬り込み、先進企業に取材する連載「C2C時代のブランディングデザイン」。番外編として、連載に大幅に加筆して発刊した書籍『ブランドストーリーは原風景からつくる』の発刊イベントから、「Ginza Sony Park」を手掛けたソニー企業社長の永野大輔氏と細谷の対談を掲載。今回はソニーが考えるブランドづくりについて聞いた後編。

バニスターの細谷正人(左)と、ソニー企業社長の永野大輔氏。対談は「Ginza Sony Park」で行った(写真/丸毛 透)
細谷 Why、What、Howをバランスよく組み合わせることは非常に難しい。どこかに偏ってしまいがちですね。
永野 おっしゃる通りです。Howの部分だけではブランドづくりは成功しません。例えばロゴデザインだけ、会社のアイコンだけをつくるのはブランド活動のうちの1つです。それらがインテグレートされ、最終的にユーザーの感動体験にまで結び付かないと、ユーザーの記憶には残りません。
特にソニーは、感動体験をWhatに置いているので、人に近づくことをすごく意識しています。人にできるだけ近づいて商品を使っていただいたりコンテンツを見ていただいたりすることを重視しています。そこでもう1つ、私が重視する点を「ブランドインターフェース」と呼んでいます。ユーザーは、ソニーという会社そのものに関心を持っているのではありません。何を通じてソニーを感じるのかといえば、商品やサービス、コンテンツです。これがソニーとユーザーをつなぐインターフェースになるわけです。

(写真/丸毛 透)
ソニー企業社長兼チーフブランディングオフィサー
1992年にソニー入社。営業、マーケティング、経営戦略、CEO(最高経営責任者)室などを経て2017年から現職。「Ginza Sony Park Project」のリーダーとして、13年からプロジェクトを推進し、18年8月9日に「Ginza Sony Park」をオープンさせた
細谷さんの原風景にあったように、細谷さんはウォークマンを通じてソニーを好きになったわけですよね。だからウォークマンがブランドインターフェースになる。ただ、次第に時代が進んでいくと、ウォークマンのようなハードよりも、音楽配信の「Spotify」のようなサービスのほうがより人に近づいている。映像でもテレビやビデオより、「Netflix」が、より人に近づいているといえる。ゲーム機の「プレイステーション」は、ソニーがハードもソフトのエコシステムもつくっている。ハードとソフトが一体になってユーザーに価値を提供しているからブランド力はすごく強いんですよ。
結局、ブランドインターフェースはタンジブル(触れることができる)とインタンジブル(触れることができない)の関係ではないでしょうか。実態や手触り感があるものと、実態がなく手触り感がないもの。今まではほとんど、タンジブルがインターフェースになっていたわけですが、今やインタンジブルが主流になってきている。インタンジブルで提供できない会社、ハードを中心とする会社のブランド価値が落ちている理由は、ここにあると思っています。この文脈でいくと、ソニービルはタンジブルですが、Ginza Sony Parkはインタンジブルです。
細谷 なるほど。ブランドインターフェースはインタンジブルでつくる時代であると捉えていいわけですか。タンジブルとインタンジブルは、どのようなバランスが良いのでしょうか。
永野 デジタル化、ネットワーク化により、ハードからサービスへと価値のシフトが起こっています。ただしインタンジブルはタンジブルがなければ存在できませんから、タンジブルがなくなることはありません。タンジブルにインタンジブルがアドオンされるのでしょうね。
2020年10月に、ソニーのイメージ調査をしました。インターネットで10~70代までの方に、ソニーの商品やサービスの中から「他社とソニーとの違いを感じるものは何ですか」と聞くと、Ginza Sony Parkを認知している人は、Ginza Sony Parkを1番に挙げました。また「未来感がある」という点では1位がロボットの「aibo(アイボ)」で2位がプレイステーション、3位がGinza Sony Park。「遊び心がある」ではプレイステーション、aibo、Ginza Sony Parkとなり、「人に優しい」ではGinza Sony Parkが1番でした。
細谷 Ginza Sony Parkも、プレイステーションやaiboと同様、ソニーを代表する商品であるということなのですね。
永野 Ginza Sony Parkはショールームではなく、休憩場所かもしれませんが、ユニークな存在であり、他社と違うということが認知されている。活動そのものがユニークで、遊び心があると感じてくれたとしたら、それはウォークマンやプレイステーションと同じように、ユーザーとソニーをつなぐブランドインターフェースになっているのでしょう。
細谷 このランキングはまさにそうですね。
未来の1歩を踏み出す勇気がブランドにつながる
永野 ユニークネスを追求するため、「What if」という意識を常に持っています。人がやらないことをやるということで、「もしソニーが○○を作ったら」を常に考えています。
「もしソニーが音楽再生機を作ったら」として出来上がったのがウォークマンです。「もしソニーがゲーム機を作ったら」でプレイステーションになった。それまでのゲーム機は、子供のおもちゃでしたが、プレイステーションはマシンになって大人も使えるようになった。価値観が変わったわけです。「もしソニーがロボットを作ったら」で、aiboが出てきた。aiboができる前はロボットと人間の関係というのはロボットが人間を助ける関係でした。ベクトルがロボットから人間に向いていた。しかしaiboは逆で、人間がロボットをかわいがる。ベクトルが逆になったのです。
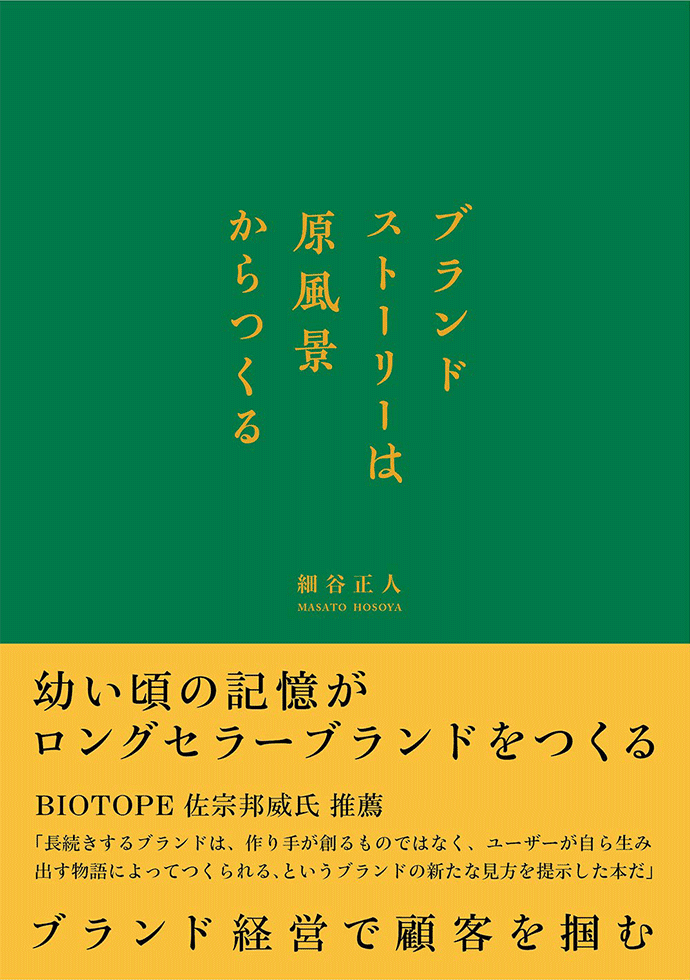
『ブランドストーリーは原風景からつくる』(日経BP)
だから「ソニーが公園を造ったら」の結果が、Ginza Sony Parkになった。ウォークマンやプレイステーション、aibo、Ginza Sony Parkに共通しているのは、「再定義をする」「世の中に問う」ことで、それが「未来の1歩になっている」ということです。音楽を聴くことを再定義した結果、利用シーンが家の中から外に移りました。ゲーム機も子供のおもちゃからマシンに変わった。ロボットは人間をサポートするのではなく、逆に人間がロボットをかわいがるものになった。いずれも再定義したわけです。
もちろん、未来の1歩を踏み出すことに対し、否定的に思う人もいます。音楽を外に出していい音が聴けるのかと言う人が出てきます。だけど、その1歩が世の中を新しくする。1歩を踏み出す勇気が問われます。
細谷 ソニーの原風景を再定義して世の中に問うことで、それが未来の1歩になっていく。そして、さらにソニーが未来に1歩を踏み出すために必要なことが勇気なんですね。
永野 勇気が未来の1歩になる。ソニーは勇気を持って世の中に問う。それが成果を上げていくと追随する人が出てくる。結果、世の中はもっと面白くなる。そうするとソニーのブランドとしての信頼感が上がっていく。これが私が考えるブランドづくりの方程式ですね。だから銀座に公園を造り、非常によかったというのが今の思いですね。コロナ禍でも、もっとチャレンジしていきますよ。
細谷 面白いお話でした。ありがとうございました。
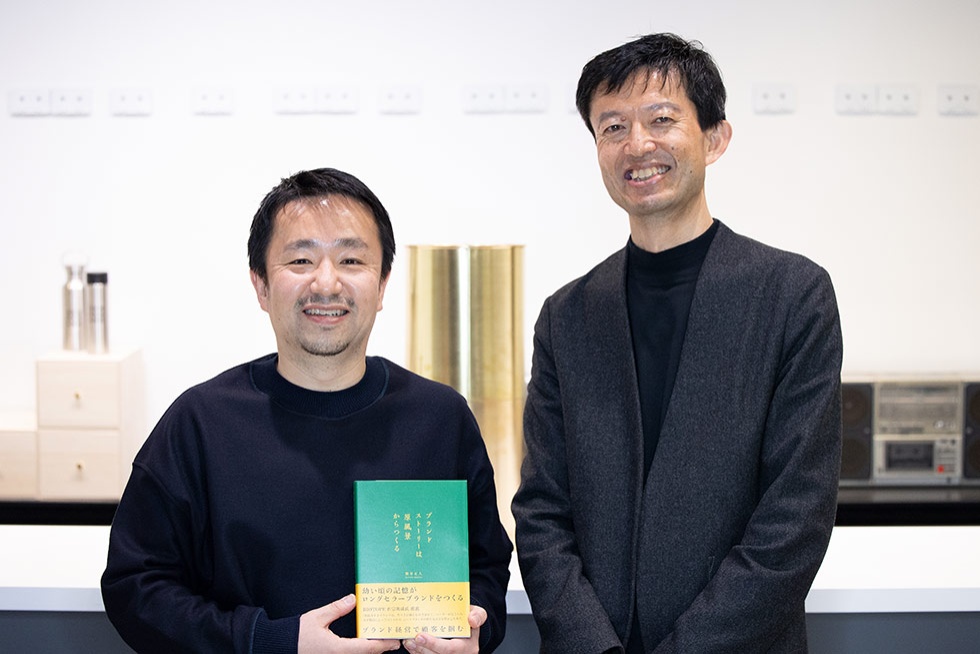
(写真/丸毛 透)
(日経クロストレンド2021年06月10日掲載の内容を転載しています。)